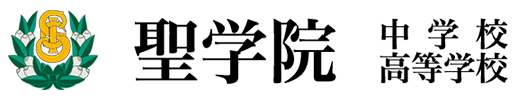【中学GIL】VIVIWAREワークショップ「学校での困りごとを解決せよ!」(前編)
中2・中3対象のGIL(Global Innovation Lab)では、5日間にわたって、自分たちの持っている知識を活用して物事を解決することに挑戦しており、毎年1学期は、VIVIWAREを用いたワークを実施しています。
このワークでは、大学生がテーマを設定し、それに基づいて生徒たちは自由な発想でプロダクト制作に取り組みます。今年度のテーマは「学校での困りごとを解決せよ!」。生徒たちに、身近な課題に目を向け、自分たちでどのように解決できるかを考えてもらうことが目的です。
日常生活の中で「これは解決が難しそうだな」と感じるようなことに対して、どうすれば解決に近づけるかを試行錯誤して考えてもらえるよう、ワークの設計と運営を行います。普段の生活では困りごとがあっても、ツールの制限などで発想の制限が出てしまいますが、VIVIWAREを使うことでアイデアの幅が広がっていきます。VIVIWAREを使うコロで広がる世界観にもついても意識しながら、ワークを作成していきます。
【Day1】
Day1では、生徒自身がテーマに沿った身の回りの課題を見つけ出し、それを解決するためのアイデアを考え、設計図の作成に取り組んでもらいました。
はじめに、生徒たちはVIVIWAREを用いたウォーミングアップとして、簡単な作品づくりに挑戦しました。その後、本題である「学校で困っていることを解決しよう」というワークに取り組みました。アイデア出しでは、「トイレや食堂が混雑している」「教室をもっと入りやすい場所にしたい」「体育が苦手で楽しめない」などの問題例を参考にしながら、自分たちの視点でできるだけ多くの困りごとを挙げてもらいました。
ワークの終盤では、挙げた困りごとをどのように解決するかを考えてもらい、その際にVIVIWAREをどう活用するかも含めて話し合い、アイデアを設計図にまとめてもらいました。ただし、設計図という形式に不慣れな生徒も多く、苦戦している様子も見られました。
今後は、設計図の書き方についても丁寧にサポートしながら、最終発表に向けて制作を進めていけるよう伴走していきます。
【Day2】
Day2では、Day1の内容を土台にしながら、制作に向けて一歩踏み出すための準備の時間となりました。前回考えたアイデアをより具体的な形にするために、振り返りと整理を中心としたワークを進めました。
まず、VIVIWAREの使い方について、特に操作が難しいと感じられていた「セル」の部分についての解説動画を視聴してもらい、理解を深めてもらいました。
続いて、前回使用したワークシートを使い、Day1で考えた内容の振り返りを行いました。どのような困りごとに注目し、それをどのように解決しようとしていたのかを改めて整理することで、思考を深める時間としました。
後半では、エイドステーション(今回の制作で使用できる素材や道具を集めた机)にある実際のモノを見に行き、自分たちが考えたアイデアにどう活用できるかを考えるワークも行いました。目で見て触れることで、アイデアに具体性や広がりが生まれていました。
今後はいよいよ本格的な制作に入ります。制作が進む中で、当初のアイデアや目的が曖昧になることもあるため、適宜サポートを行いながら、最終発表に向けてプロダクトを完成できるよう伴走していきます。
【担当大学生コメント】
三浦:今年度は、初めて「身近なこと」をテーマにワークを設計しています。例年は「未来の〇〇はどうなっているのか」といった、未来を自由に想像するテーマで取り組んできました。そのため、大学生としては、身近なテーマでは逆に困りごとが見つけづらいのではないかと少し心配していました。しかし、生徒たちは自分たちなりの視点で身近な困りごとを見つけ出し、積極的に解決のアイデアを出しています。どんなプロダクトが最終的に生まれるのか、とても楽しみです。
比嘉:今年のVIVIWAREでの活動は、各自で決めたテーマに沿って工作をするという大まかな筋は去年のままで、こっちで出すお題を「学校での困りごとに対処しよう」に指定しました。やはり、去年から引き続き参加しているメンバーは進行度が早かったり、アイデア自体が面白かったりして大学生も完成品を見るのが楽しみです。特に「女子がいない」という問題をプログラミングで解決しようという班があり、大学生からはとても人気でした。
【担当教員コメント】
山本・田邊:今回のGILはあたらしい知識を身に着けるのではなく、既存の知識をどのように自分たちの生活に生かすのかというポイントに着目して行われていました。自分の困りごとを解消するために自分たちの手で解決策を見つける。さらにそれを実行する。このプロセスを理解することで、今後の自らの学びに良い影響を及ぼしてくれるでしょう。後半戦で、彼らがどんなクオリティで、何を変えるために作るのか非常に楽しみです。