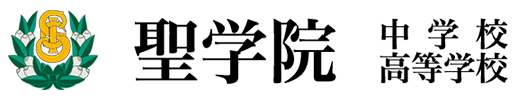【高2】戦後80年 高校生が考える戦争と平和シンポジウム 開催レポート
去る11月23日(日)、LINEヤフー本社内の「LODGE」にて、「戦後80年 高校生が考える戦争と平和シンポジウム」が開催されました。
本シンポジウムは、聖学院、駒込、東京立正、中村、田園調布学園の5校が参加し、戦争と平和をテーマに高校生たちが自らの研究成果を発表する場となりました。また、本校卒業生で学習院大学の佐藤佑哉くんも研究発表を行いました。
【本校生徒による発表内容】
聖学院からは、高校2年生の三奈木くん、塩田くん、塩﨑くん、菊池くん、早野くん、金子くん、高木くん、近藤くん、中島くん、木原くんの10名が登壇しました。彼らは、ウクライナ、広島、沖縄をテーマに深く学んだ内容をもとに、それぞれが導き出した独自の考察を発表しました。
特に印象的だった、生徒たちの考察の一部をご紹介します。
広島:記憶を語ることの重み
広島の被爆者の方々は、みなさんが記憶を語りたい訳ではない。辛すぎて語れない人もいる。私たちは、そうした「語れない苦悩」にも目を向ける必要がある。
ウクライナ:平和か、勝利か
ウクライナでは、「平和」という言葉よりも、「勝利」という言葉のほうに現実味があるという。勝利しないと対等になれない、領土や文化が脅かされるため、「勝利」しか求めなくなる。だからこそ、私たちは、戦争を避けなければならない。
沖縄:加害性への視点
沖縄戦を米軍側から見たらどうなるか。なぜ米軍は火炎放射機を使ったのか。それは、民間人を装った日本兵によるゲリラ戦や、保護しようとした民間人の集団自決に衝撃を受け、恐怖を感じたからだろう。日本人側の国民性や日本の加害性にも目を向けなければならない。
平和について:「平和」という言葉の再定義
「平和」という言葉を軽々しく使うべきではないと考えた。「生き残ってしまった」という体験者の苦悩を学んだら、「平和」という言葉は重く、簡単に使えなくなった。
【結び】
引率した大川功教諭からは、「ありきたりな平和学習ではなく、生徒が戦争と平和について主体的に探究し、現場を踏んで感じたことを言葉にしてくれた」との報告がありました。
生徒たちは、戦争の現実から目を背けず、多角的な視点、特に加害性や言葉の重みにまで踏み込んだ考察を展開し、高校生ならではの真剣な問いを投げかけました。この貴重な経験が、彼らの今後の学びと平和への意識をさらに深める糧となることを期待します。