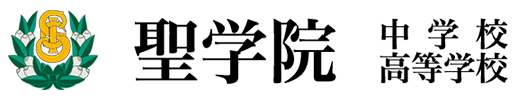【高校GIC】貧困vs起業ゼミ・大竹道茂氏をお招きし江戸東京野菜の講演会を開催
6月21日(土)に、高校GIC(Global Innovation Class)の貧困vs起業ゼミは、「江戸東京野菜には物語がある〜ブランディングと透明化の未来〜」と題した講演会を開催しました。参加者は17名です。
本講演会は、都市農地の保全と文化継承を半世紀にわたり追求されてきた大竹道茂氏を講師としてお迎えし、江戸東京野菜が紡いできた歴史と、それをいかに現代に活かすかを考える貴重な機会となりました。大竹氏は、JA東京中央会で都市農地への宅地並課税に警鐘を鳴らしつつ、平成元年から『江戸・東京ゆかりの野菜と花』などの刊行を通じて復活運動を推進、現在はNPO法人江戸東京野菜コンシェルジュ協会会長として食育プログラムや収穫体験を展開し、3000日を超えるブログ「江戸東京野菜通信」で全国へ活動を広げておられます。
講演では、小松菜や練馬大根をはじめとする各品種の由来や、都市化の進行によって失われつつある農地と地域文化の関係、さらにはSDGsの観点から都産都消や飢餓撲滅、気候変動対策などとの連携可能性が多角的に語られました。中でも、「文化は要約されると本質を失う」という言葉は深く胸に刻まれました。伝統野菜における“揃いの悪さ”も、人と土地、時間が折り重なった証であり、そのまま受け止めてこそ真価が見えてくる──この示唆を通じて、参加者自身の活動にも新たな視座がもたらされました。
参加した高校生のアンケート結果からは、事前知識の有無にかかわらず89%が何らかの社会貢献活動に関心を寄せ、66%以上が今後具体的なアクションを起こしたいと回答したことが明らかになりました。「野菜は語り継がれる文化である」「都市と農が結ぶ記憶を回復できる可能性を感じた」といった声が多く、単なる知識獲得にとどまらず、行動への意欲を醸成できた点が大きな成果です。
江戸東京野菜は、都市に刻まれた人々の暮らしと営みの記憶を伝える「生きた資料」であり、その継承は未来の社会を形づくる重要な営みです。今後もゼミとしては、江戸東京野菜の滝乃川ゴボウ茶や滝野川ニンジンドレッシングなどの商品開発を続けていきたいと思っています。そしてこのことを通じて、「文化を要約せず、現代の文脈で語り直す」挑戦を続け、ひと多くの生徒が「農」の課題を「知るだけでなく、継ぎ、育てる」入口を広げていく場づくりをしていきたいと思っています。(担当教諭:相澤 睦)